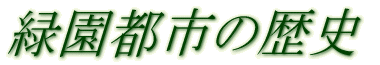| 「緑園都市」開発の経緯 (1926年以降) |
| 昭和のはじめ |
東海道線の戸塚駅から大船駅にかけて工場の進出が目立ってくる。柏尾川から工業用水を 引いた工業地帯の形成である。 |
| 昭和13年頃より |
鎌倉郡北部の1町7ヶ村を横浜市に編入しようとする動向がでてきて、この市域拡張により昭和14年戸塚区が誕生する。 |
| |
岡津地域は奈良時代から鎌倉郡に属していたが、その歴史も終わり戸塚区の仲間入りをする。 |
| 戦後 |
戸塚区は東京都心部のベットタウンとして人口が急増し、開発も進められるようになる。 |
| 昭和22年 |
新学制の発足により、岡津中学校が開校する。戸塚区にある中学校は、この岡津中学を入れて5校となる。 |
| 昭和44年 |
戸塚区から瀬谷区が分区するが、その後も戸塚区の人口は増え続け40万人を突破する。 |
| 昭和51年 |
横浜西部地域の人口増加に伴い、県立高校の100校目として岡津高校が開校する。 |
| 昭和52年 |
相鉄いずみ野線が開通し、同時に緑園都市の歴史が始まる。 |
| 現在 |
消防出張所、交番、フェリス女学院大学、二つの小学校、複合福祉施設などのいろいろな施設が出来て変化してきているが、西には富士山、丹沢連峰がそびえ、南には鎌倉山が見られる環境に恵まれた地域であることは変化していない。
”相鉄いずみ野線のコア・シティ”をスローガンに調和の取れた安全で住みよい街として今日に至る。
|
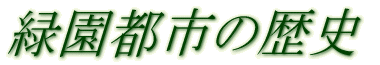
![]()